気候変動対応
気候変動対応
現在、世界各地で暴風雨、洪水、干ばつといった異常気象による被害が増加しています。また、今後脱炭素社会へ移行するために規制や市場が大きく変化することが考えられます。当社は、このような気候変動による社会的・経済的影響について、持続可能性が問われる重要な経営課題と認識し、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を2022年6月に表明しました。TCFDの提言に従い、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の情報開示フレームワークに基づき積極的な情報開示に努めます。また、気候変動に対応する具体的な対策を講じ、取り組んでまいります。
1. ガバナンス体制 ~サスティナビリティ推進体制~
当社は、気候変動問題を含めた環境問題への対応を経営の重要な課題の一つとして位置付け経営戦略と一体的に推進していくため、取締役会の諮問機関としてサスティナビリティ委員会を設置しています。
サスティナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、気候変動を含めた環境問題をはじめ、サスティナビリティに関する経営課題について確認および審議しています。
また、気候変動に関するリスクと機会については、リスク管理委員会で分析および対策決定を行っています。
サスティナビリティ委員会およびリスク管理委員会にて審議された内容は、各委員会から定期的に年1回および必要に応じて随時取締役会に報告され、取締役会にて気候変動に関する重要なリスクと機会について審議のうえ重要事項を決定し、対応の指示およびその進捗に対する監督を行っています。
| 委員会名 | 役割 | 開催回数 |
|---|---|---|
| 取締役会 | 気候変動対応の審議・重要事項決定・監督 | 12回/年 |
| サスティナビリティ委員会 | 気候変動対応の確認・審議 | 2回/年 |
| リスク管理委員会 | 気候変動リスク・機会の分析・対応決定 | 4回/年 |
2. 戦略
当社は、サプライチェーン全体を対象に気候変動に伴い生じ得るリスクと機会について洗い出し、事業への影響の分析および考察を行っています。分析にはIEAが公表する4℃シナリオと1.5℃未満シナリオ(パリ協定の合意に整合)を用いて、それぞれの世界観における2030年時点の当社への影響について考察を行っています。
- ●4℃シナリオ
産業革命期頃の世界平均気温と比較して2100年頃までに平均4℃上昇し、台風や大雨などの異常気象の激甚化が拡大する世界観
- ●1.5℃未満シナリオ
炭素税の導入や再エネ政策などカーボンニュートラルを目指した取り組みにより1.5℃に気温上昇が抑制される世界観
分析結果
各シナリオで想定されるリスクと機会を特定しました。4℃シナリオでは、台風や大雨などの異常気象の激甚化に伴い、操業停止や物流機能の停止による対応コストの増加が大きなリスクになると推測されます。
一方で1.5℃未満シナリオでは、世界的な脱炭素の取り組みにより炭素税・排出権取引の導入や化石燃料由来の電力価格が高騰することが予測され、操業コストの増加が大きなリスクと推測されます。
当社は、IEAのシナリオを用いて炭素税の導入、電力価格の高騰、金属価格の変化による事業への影響度を確認しています。また、物理的リスクにおいても、RCP8.5シナリオ・RCP2.6シナリオ、 治水経済調査マニュアル をもとに洪水や高潮が発生した際の事業への影響度を確認しています。
また、リスクだけでなく多くの機会も確認しております。脱炭素社会の進展に伴うEV関連製品の需要増加や水素技術の普及による水素関連事業の拡大は大きな機会になると推測されます。
気候変動に関するリスク・機会一覧表
評価 小:財務的影響小 中:財務的影響中 大:財務的影響大
| 気候関連問題による影響 | 時間軸 | リスクと機会(想定される事象) | 影響度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4℃ | 1.5℃ | |||||
| 脱 炭 素 経 済 へ の 移 行 に 伴 う 影 響 |
中期~長期 | 炭素税・排出権取引の導入 | リスク | ・事業コストの増加 | 小 | 大 |
| 機会 | ・CO2削減等環境に貢献する商品の売上増加 | |||||
| 中期~長期 | GHG排出規制への対応 | リスク | ・省エネ設備への更新コストの増加 | 小 | 大 | |
| 機会 | ・CO2排出量が少ない商品の売上増加 | |||||
| 中期~長期 | 再エネ・省エネ政策 | リスク | ・再エネ価格上昇による事業コストおよび省エネ設備への更新によるコストの増加 | 小 | 大 | |
| 機会 | ・顧客の省エネにつながるサービス需要、太陽光・水力・バイオマス発電の新規ビジネス機会の増加 | 短期~長期 | 低炭素技術の進展 | リスク | ・空圧機器から電動機器へ急激な需要のシフトに対応できなかった場合の売上減少 ・脱炭素技術開発に向けた研究開発費増加 |
小 | 大 |
| 機会 | ・二次電池製造工程用商品、水素関連ビジネス向け商品、生産設備のIoT関連機器、半導体関連機器等の売上増加 | 気 候 変 動 の 物 理 的 な 影 響 |
短期~長期 | 異常気象の激甚化 | リスク | ・災害による生産拠点の被害やサプライチェーン寸断による生産停止、事業継続への影響 ・BCP対策費用の増加 |
大 | 小 |
| 機会 | ・生産拠点の移転や再編に伴う設備投資、人に依存しないモノづくりの推進によるFA機器需要の増加 ・被災からの復興に関わるメンテナンスビジネスの拡大 | |||||
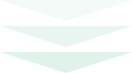
気候変動に関するリスク・機会に対する当社の対応
| 脱 炭 素 経 済 へ の 移 行 に 伴 う 影 響 |
リスク低減 | ・サプライチェーン全体のCO2削減目標の設定 詳細は本ページ「4.指標と目標 (2) 目標と取り組み」に記載 |
| 機会獲得 | ・包材ロスが少ない薬品包装機の販売強化 詳細はこちら(社会へ広がるCKDの環境・社会貢献型商品) |
|
| 気 候 変 動 の 物 理 的 な 影 響 |
リスク低減 | ・災害時の防災管理規定/BCP規定の整備 詳細はこちら(CKDレポート2024 P.63-64) |
3. リスク管理
CO2排出量削減をはじめとする当社グループの様々な重要課題について、本社管理部門、各事業及びグループ会社にて企業価値の向上及び経営目標の達成を阻害するリスクと機会を洗い出しています。その抽出結果をもとに、リスク管理委員会にて発生する頻度と発生した時の影響度からリスク・機会の重要度を評価し特定しています。また、特定されたリスク・機会については対策を検討し、取締役会に報告し共有しています。
このように、気候変動リスクを含め統合的にリスクの管理と評価を行っています。
4. 指標と目標
(1) 指標
| 指標 | 単位 | 2023年度実績 |
|---|---|---|
| CO2排出量(相殺前) (注)1、2、3 | t-CO2 | 38,787 |
| CO2排出量(相殺後) (注)4 | t-CO2 | 36,165 |
| CO2排出量(売上原単位)(注)4 | t-CO2/億円 | 26.9 |
| CO2排出量削減率(総量、2022年度対比)(注)4 | % | 12.9 |
| CO2排出量削減率(売上原単位、2013年度対比)(注)4 | % | 34.5 |
- (注)1.CO2排出量はスコープ1・2の合計です。
- 2.スコープ1は、当社、国内子会社および在外子会社 (工場のみ) の主な排出量の合計で、環境省HP公開の排出係数を使用しています。
- 3.スコープ2は、当社、国内子会社および在外子会社 (工場のみ) の主な排出量の合計で、境省HP公開の基礎排出係数を使用しています。
なお、当社営業所および在外子会社 (工場) は本社と同じ排出係数を使用しています。 - 4.J-クレジット制度、グリーン電力証書によるCO2排出量の相殺分を含みます。
(2) 目標と取り組み

中長期目標(CO2排出量削減)
CKDグループでは“脱炭素社会の実現”に貢献するため、2050年度CO2排出量実質ゼロを基準として、バックキャスティングによりCO2排出量の中長期削減目標を新たに設定し、CO2排出量削減に取り組んでいます。
2030年度 CO2排出量 50%削減 (総量、2022年度対比)
2030年度 CO2排出量 50%削減(売上高原単位、2013年度対比)
2050年度 実質排出ゼロ
- ※2023年度よりCO2排出量削減目標として「2030年度 50%削減 (総量、2022年度対比) 」を追加設定しました。
具体的削減方策として以下の取り組みを推進していきます。
- ●徹底した省エネルギー改善の推進
- ●再生可能エネルギーの拡充(太陽光発電設備等の導入)
- ●再生可能エネルギー由来電力の活用
再生可能エネルギーへの取り組み
CO2排出量削減目標の達成に向けて、国内外の工場で太陽光発電システムを導入しています。
また、CO2排出削減の新たな取り組みとして、J-クレジット制度の活用によるカーボンオフセットや水力発電由来の「グリーン電力」を利用しています。
- ●国内外の工場で太陽光発電システムを導入

本社・小牧工場
-

春日井工場
-

東北工場
-

シコク精工工場
-

中国工場
-

タイ工場
- ●グリーン電力の利用
-
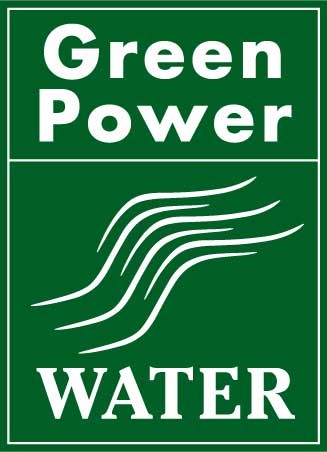
-

犬山工場



